🧠 5択クイズ から復習に来た方へ
下のボタンから、要点解説の本文へジャンプできます 👇
🧩 まだクイズを解いていない方は、こちらから挑戦!
👉 【循環器疾患】5択クイズで学ぶ!心弁膜症(僧帽弁・大動脈弁)の代表4疾患
🔰 この記事について
- 本記事は、心弁膜症についての要点解説記事です(※クイズは別記事)。
- 基礎から整理して学びたい方は、この要点解説から読み進めてください。
🖊️ この記事で学べる内容
以下の疾患について、特徴や違いのポイントをまとめています。
🩺 学習の進め方
この心弁膜症シリーズは、
「5択クイズ編」と「要点解説編」 の2本立てになっています。
おすすめの使い方👇
- 最初に 5択クイズ に挑戦して理解度チェック
- できなかった部分を、要点解説記事(本記事) でしっかり整理
- 最後にもう一度クイズを解いて、知識を定着
💡 学習のポイント
🔍 要点まとめ|心弁膜症の特徴を整理
🧭 本文内の主要項目へジャンプ
▶ 心弁膜症(総論)
▶︎ 僧帽弁狭窄症(MS)
▶︎ 僧帽弁閉鎖不全症(MR)
▶︎ 大動脈弁狭窄症(AS)
▶︎ 大動脈弁閉鎖不全症(AR)
重要ポイントだけ一気に復習したい方はこちら👇
心弁膜症(心弁膜性疾患)
- 心弁膜症とは、心臓弁やその支持組織(腱索・乳頭筋など)の異常によって、弁の開閉が障害される疾患です。
- その結果、血流の一方向性が保てなくなり、心臓に過負荷がかかります。
- 主な病態は次の3つに分類されます。
- 弁狭窄症:弁が十分に開かず、血液が流れにくくなる状態
- 弁閉鎖不全症(逆流症):弁が完全に閉じず、血液が逆流する状態
- 混合型:狭窄と逆流が同時にみられる状態
正常な弁の動き
- 心臓の弁は、血液が一方向に流れるように「開閉」をくり返しています。
- 弁膜症の理解には、まず正常時にどの弁がいつ開き、いつ閉じるのかを把握することが大切です。
| 時期 | 心室の状態 | 開いている弁 | 閉じている弁 |
|---|---|---|---|
| 拡張期 | 心室が拡張し、 血液を受け入れる | 房室弁 (僧帽弁・三尖弁) | 動脈弁 (大動脈弁・肺動脈弁) |
| 収縮期 | 心室が収縮し、 血液を送り出す | 動脈弁 (大動脈弁・肺動脈弁) | 房室弁 (僧帽弁・三尖弁) |

(管理人)
心弁膜症を理解するためには、「正常な弁の動き」を理解することが必須です。
心臓弁については、2章の【循環器】心臓の弁(heart valve)の記事でも復習しておきましょう。
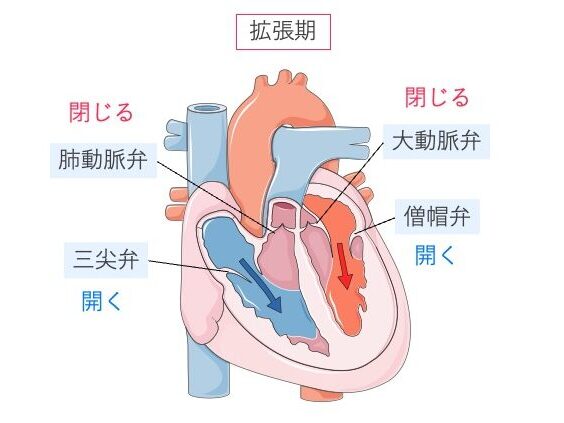
心室拡張期には房室弁(僧帽弁・三尖弁)が開き、
動脈弁(大動脈弁・肺動脈弁)は閉じている。
血液が心房から心室へ流入する。
出典:SMART SERVIER MEDICAL ART(CC BY 3.0)
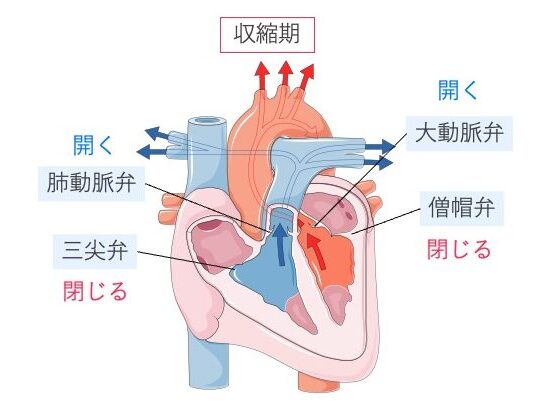
心室収縮期には動脈弁(大動脈弁・肺動脈弁)が開き、
房室弁(僧帽弁・三尖弁)は閉じている。
血液が心室から大動脈・肺動脈へ駆出される。
出典:SMART SERVIER MEDICAL ART(CC BY 3.0)
🧭 本文内の主要項目へジャンプ
▶ 心弁膜症(総論)
▶︎ 僧帽弁狭窄症(MS)
▶︎ 僧帽弁閉鎖不全症(MR)
▶︎ 大動脈弁狭窄症(AS)
▶︎ 大動脈弁閉鎖不全症(AR)
僧帽弁狭窄症:Mitral Stenosis (MS)
概念
- 僧帽弁が狭くなり、拡張期に左心房から左心室への血液流入が障害される状態です。
原因
- 主な原因は リウマチ熱の後遺症 で、女性に多くみられます。
👉 リウマチ熱について詳しくはこちら

(管理人)
リウマチ熱は現在では減少していますが、
試験では “僧帽弁狭窄症=リウマチ熱の後遺症”として
問われることも多いです。
病態
- 僧帽弁口が狭くなることで、拡張期に左心房から左心室への血流が障害されます。
- その結果、左心房圧が上昇して左心房拡大をきたし、心房細動のリスクが増加します。
- 左心房圧の上昇は肺静脈・肺毛細血管に波及し、肺うっ血・肺高血圧へと進行します。
- さらに進行すると右心系に負荷がかかり、右室肥大・右心不全をきたすようになります。
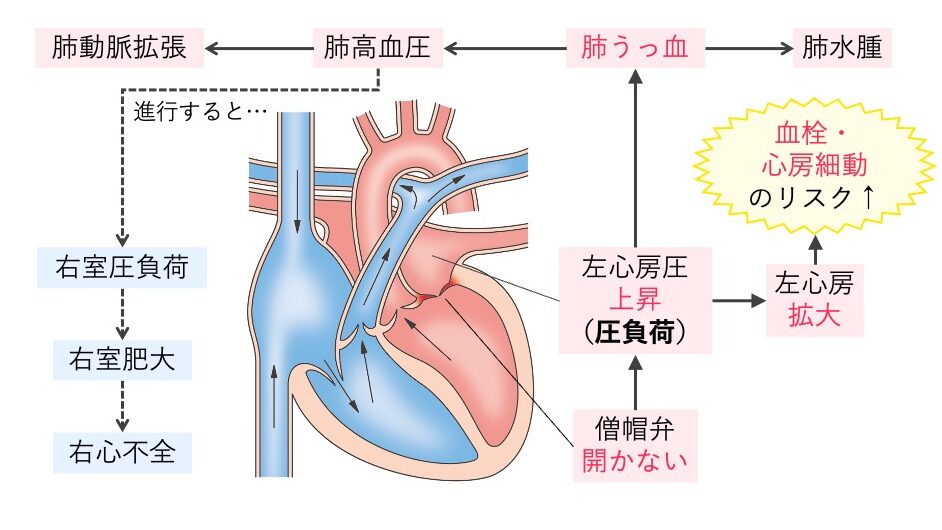
僧帽弁が十分に開かず、左心房圧上昇から
左房拡大・肺うっ血・肺高血圧・右心不全
へと進展する血行動態の模式図。
出典:北海道心臓協会 フリーイラスト集
👉 圧負荷については こちらで解説
症状
- 肺うっ血による労作性呼吸困難が出現します。
- 心房細動によって動悸や脈不整を起こすことがあります。
- 進行すると右心不全症状がみられることもあります。
診断のポイント
- 心音ではⅠ音の亢進や、拡張期の「遠雷様雑音」が特徴です。
👉 心音(Ⅰ音やⅡ音)については、こちら - 心エコーでは弁口面積の減少が確認されます。
🧭 本文内の主要項目へジャンプ
▶ 心弁膜症(総論)
▶︎ 僧帽弁狭窄症(MS)
▶︎ 僧帽弁閉鎖不全症(MR)
▶︎ 大動脈弁狭窄症(AS)
▶︎ 大動脈弁閉鎖不全症(AR)
僧帽弁閉鎖不全症(僧帽弁逆流症):Mitral Regurgitation (MR)
概念
- 僧帽弁が完全に閉じず、収縮期に左心室から左心房へ血液が逆流する状態です。
- Regurgitation は「逆流」という意味で、僧帽弁逆流症とも呼ばれます。
原因
- 主な原因は以下の通りです。
- 僧帽弁逸脱症
(僧帽弁が収縮期に左心房側へ膨らむ病態。弁がしっかり閉じず逆流を生じる) - リウマチ性変化
- 腱索断裂
- 左心室拡大(心筋梗塞や心不全によるもの)
- 僧帽弁逸脱症
病態
- 僧帽弁が完全に閉じなくなると、収縮期に左心室から左心房へ血液が逆流します。
- 逆流によって左心房が容量負荷を受けて拡大し、心房細動のリスクが高まります。
- 左心房への逆流は肺静脈に圧を伝え、肺うっ血を引き起こします。
- 左心室もまた、逆流により有効な拍出量が減少し、代償的に拡大・肥大をきたします。
- 進行すると、肺高血圧から右心系にも負荷がかかり、最終的には右心不全に至ることがあります。
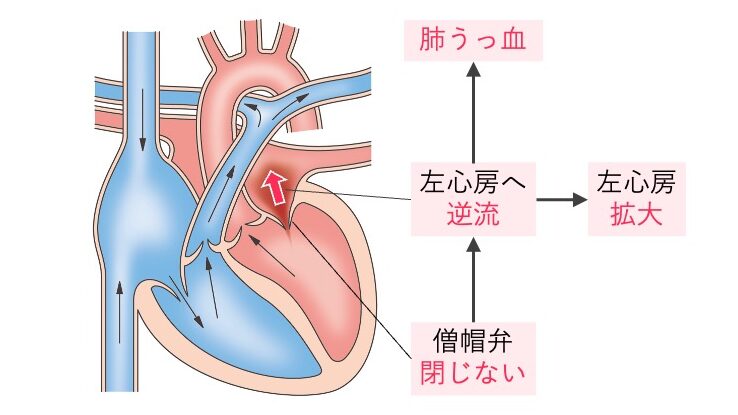
僧帽弁が閉じず、収縮期に左室から左房へ血液が逆流し、
左房拡大・肺うっ血をきたす血行動態の模式図。
出典:北海道心臓協会 フリーイラスト集
症状
- 左心不全症状(労作時呼吸困難、動悸、息切れ、易疲労感)
- 進行例では発作性夜間呼吸困難や起坐呼吸がみられます
診断のポイント
- 聴診:Ⅰ音の減弱、Ⅲ音の出現、全収縮期逆流性雑音が特徴です
- 心電図:左室肥大や心房細動(AF)がみられることがあります

(管理人)
雑音の時期は「弁がトラブルを起こすタイミング」で考えると整理できます。
僧帽弁が狭窄すると、拡張期にトラブルが生じる → 拡張期雑音
僧帽弁が閉まらないと、収縮期にトラブルが生じる→ 収縮期雑音
※大動脈弁では逆になるので注意しましょう。
治療
- 内科的治療:心不全に対する薬物治療を行います。
- 外科的治療:僧帽弁形成術や僧帽弁置換術が選択されます。
- 開胸し、一時的に人工心肺装置を用いて行います。
- 外科的治療には 弁形成術 と 弁置換術 があります。
弁形成術
- 人工弁輪などを用いて、患者自身の弁を修復し、機能を回復させる方法です。
- 可能であれば第一選択となります。
弁置換術
- 障害された弁を取り除き、生体弁や機械弁に置き換える方法です。
- それぞれの弁には特徴があり、患者の年齢や合併症に応じて選択されます。
🧭 本文内の主要項目へジャンプ
▶ 心弁膜症(総論)
▶︎ 僧帽弁狭窄症(MS)
▶︎ 僧帽弁閉鎖不全症(MR)
▶︎ 大動脈弁狭窄症(AS)
▶︎ 大動脈弁閉鎖不全症(AR)
大動脈弁狭窄症:Aortic Stenosis (AS)
概念
- 大動脈弁が狭くなり、収縮期に左心室から大動脈への血液駆出が障害される病態です。
原因
- 大動脈二尖弁(本来3つの弁尖が2つしかなく、若年で弁狭窄をきたしやすい)
- 動脈硬化による弁の石灰化
- リウマチ性変化
病態
- 大動脈弁が十分に開かなくなると、左心室から大動脈への血液駆出が障害されます。
- その結果、心拍出量が低下し、血圧低下や失神・めまいなどを引き起こすことがあります。
- 左心室は駆出抵抗に対して収縮期圧が上昇し、圧負荷により肥大します。
- 肥大した左心室は拡張不全を起こし、左心房圧上昇から肺うっ血へとつながります。
- 進行すると冠血流が低下し、労作時の狭心痛の原因となります。
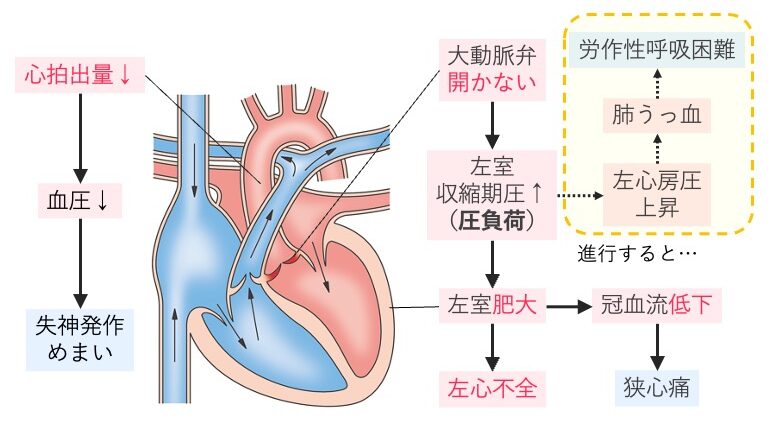
大動脈弁が開かず、左室圧負荷により左室肥大・拡張不全をきたし、
心拍出量低下や狭心痛・失神のリスクが生じる模式図。
出典:北海道心臓協会 フリーイラスト集
👉 圧負荷については こちらで解説
症状
- 初期は無症状で経過することが多いです。
- 左心不全により息切れや狭心痛が出現します。
- 心拍出量の低下により、失神発作・遅脈・小脈・血圧低下がみられることがあります。
- 重症例では突然死をきたすこともあります。

(管理人)
大動脈弁狭窄症では “三徴” が試験で定番 です。
狭心痛・失神発作・労作時呼吸困難
この3つが出てきたら大動脈弁狭窄症をまず疑う、と覚えておきましょう。
突然死のリスクもあるので臨床的にも重要です。
大脈(だいみゃく)
- 脈圧(最高血圧-最低血圧)が大きい脈を指します。
- 動脈硬化、大動脈弁逆流、バルサルバ洞動脈瘤破裂、動脈管開存などでみられます。
小脈(しょうみゃく)
- 脈圧が小さい脈を指します。
- 心ポンプ機能が低下しているときや、大動脈弁狭窄、心室中隔欠損などでみられます。
速脈(そくみゃく)
- 脈が急速に立ち上がり、急速に消失する状態です。
- 大脈は速脈となります。
- 「頻脈」とは異なる概念です。
遅脈(ちみゃく)
- 脈が徐々に立ち上がり、徐々に消失する状態です。
- 小脈は遅脈となります。
- 「徐脈」とは異なる概念です。
診断のポイント
- 心音:収縮期駆出性雑音、胸壁でスリルを触知することがあります。
- 心電図・胸部X線:左室肥大や左脚ブロックの所見がみられます。
- 心エコー:弁口面積を評価し、重症度を判定します。
治療
- 内科的治療:心不全に対する薬物療法を行います。
- 外科的治療:大動脈弁置換術(AVR)が基本であり、症例によっては大動脈弁形成術も行われます。
- 重症の大動脈弁狭窄症に対する治療法です。
- カテーテルを用いて人工弁を心臓の大動脈弁部に留置します。
- 2002年にヨーロッパで初めて施行され、日本では 2013年に保険適用 となりました。
- 従来の外科的人工弁置換術(開胸・人工心肺使用)とは異なり、開胸せず人工心肺を用いないため、体への負担が少ないのが特徴です。
- そのため 高齢者や手術リスクが高い患者でも適応可能 であり、近年は標準的な治療法の一つとなっています。
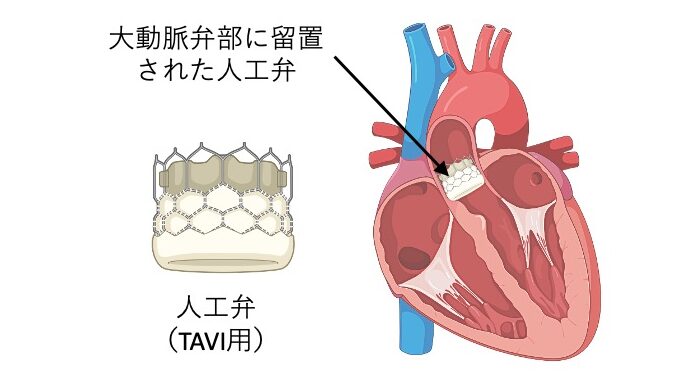
大動脈弁狭窄症に対して用いられる経カテーテル大動脈弁治療(TAVI)の人工弁と、その留置部位を示す模式図。
Created with BioRender.com
🧭 本文内の主要項目へジャンプ
▶ 心弁膜症(総論)
▶︎ 僧帽弁狭窄症(MS)
▶︎ 僧帽弁閉鎖不全症(MR)
▶︎ 大動脈弁狭窄症(AS)
▶︎ 大動脈弁閉鎖不全症(AR)
大動脈弁閉鎖不全症(大動脈弁逆流症):Aortic Regurgitation (AR)
概念
- 大動脈弁が完全に閉じず、拡張期に左心室へ血液が逆流する疾患です。
- Regurgitation は「逆流」という意味で、大動脈弁逆流症とも呼ばれます。
原因
- 主な原因は以下の通りです。
- その他、梅毒や膠原病、動脈硬化なども原因となることがあります。
病態
- 大動脈弁が完全に閉じないため、拡張期に大動脈から左心室へ血液が逆流します。
- 左心室は逆流によって容量負荷を受け、拡大します。
- 左心室拡大に伴って拡張期圧が上昇し、左心房へと波及して左心房圧上昇をきたします。
- その結果、肺静脈系に血液がうっ滞し、肺うっ血が生じます。
- 進行すると左心室の収縮機能が低下し、心不全へと至ることがあります。
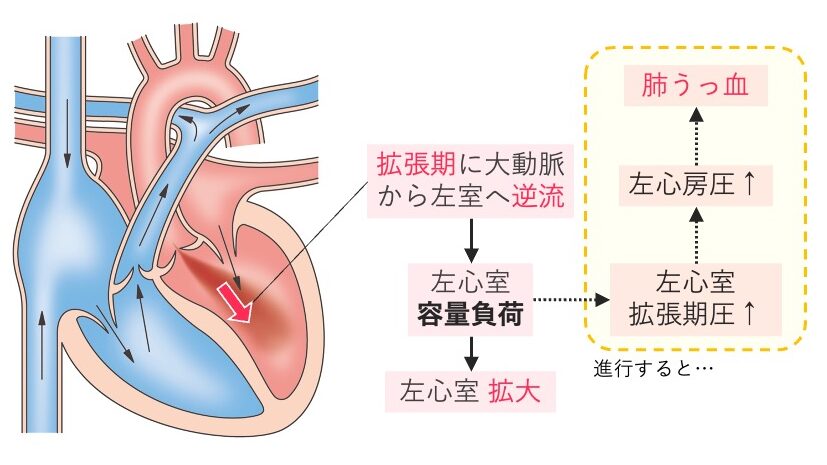
大動脈弁が閉じず、拡張期に大動脈から左室へ逆流が生じ、左室拡大・肺うっ血をきたす血行動態の模式図。
出典:北海道心臓協会 フリーイラスト集
👉 容量負荷については こちらで解説
症状
- 慢性例では初期は無症状で経過することがあります。
- 進行すると左心不全症状が出現します。
- 主な症状:動悸、呼吸困難、狭心痛
- 大脈(脈圧増大)、速脈などの脈の異常が特徴的です。
- 突然死は比較的少ないとされています。
診断のポイント
- 心音:拡張期の灌水様雑音(拡張早期雑音で漸減性・高調音)
- 心電図・胸部X線:左心室肥大の所見
治療
- 内科的治療:心不全に対する薬物治療
- 外科的治療:大動脈弁置換術(AVR)が基本となります。

(管理人)
弁膜症の病態を理解するうえでは、
血流による心臓への「圧負荷」や「容量負荷」の違い
を意識すると整理しやすくなります。
圧負荷
- 狭窄症などで血液を送り出すのに高い圧力が必要になる状態です。
- 心室は厚く肥大して対応します(心筋の肥大)。
- 例:大動脈弁狭窄症、肺動脈狭窄症
容量負荷
- 閉鎖不全症などで血液が逆流し、処理すべき血液の量が増える状態です。
- 心腔は拡大して対応します(心腔の拡張)。
- 例:僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁閉鎖不全症

(管理人)
肥大は心筋そのものが厚くなること、拡大は心腔が広がることです。
似ている言葉ですが、意味は全然違うので混同しないようにしましょう。
🧭 本文内の主要項目へジャンプ
▶ 心弁膜症(総論)
▶︎ 僧帽弁狭窄症(MS)
▶︎ 僧帽弁閉鎖不全症(MR)
▶︎ 大動脈弁狭窄症(AS)
▶︎ 大動脈弁閉鎖不全症(AR)
📝 チェックリストで心弁膜症の最重要ポイントを一気に確認!

(管理人)
各疾患の重要キーワードだけをリストアップしました。
試験の直前チェックに!
🧭 本文内の主要項目へジャンプ
▶ 心弁膜症(総論)
▶︎ 僧帽弁狭窄症(MS)
▶︎ 僧帽弁閉鎖不全症(MR)
▶︎ 大動脈弁狭窄症(AS)
▶︎ 大動脈弁閉鎖不全症(AR)
※ 記事作成には正確を期しておりますが、内容に誤りや改善点がございましたら、お知らせいただけますと幸いです。
今後の教材作成の参考にさせていただきます。
💯 心弁膜症 の理解度をクイズでチェック!
👇 以下の5択クイズ記事で、要点解説で学んだ内容をチェックできます。
🔗 循環器疾患の学習に役立つ関連記事
👇 循環器系の基本的な解剖生理を復習したい人はこちら
👇 循環器疾患の 5択クイズの記事一覧 はこちら
👇 循環器疾患の 図解つき要点解説の記事一覧 はこちら
👇 循環器疾患の 総合演習 はこちらから挑戦できます!
👇 循環器疾患の 頻出問題だけ 短時間で復習したい方はこちら
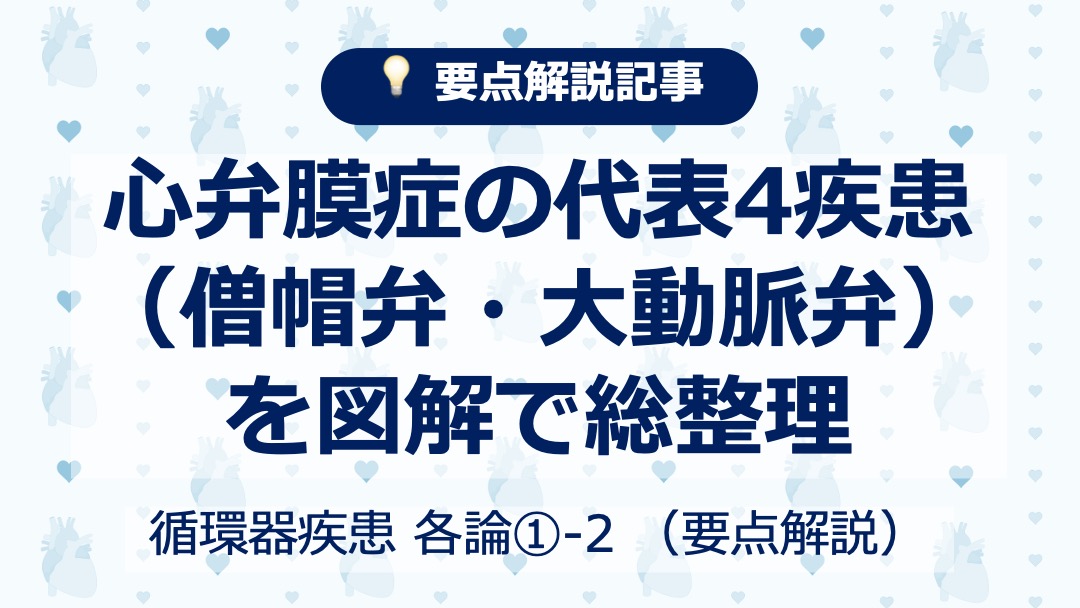
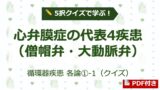

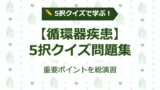
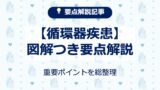
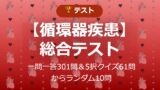


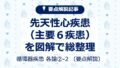
コメント