
脳出血や脳梗塞の違いをよく理解していなくて…
それぞれの特徴を教えてください!

(管理人)
もちろんです!
血管が「破れる」のか「詰まる」のかで、発症の仕方や症状が全く異なります。
クイズを解きながら、区別していきましょう!
🔰 この記事について
本記事は、「解いて覚える」をコンセプトにした脳血管疾患の5択クイズ記事です。
(※詳細な要点解説は別記事にしています)
診療情報管理士の認定試験(基礎・医学編)をはじめ、医療系国家試験の出題範囲を中心に構成しています。
出題対象は以下のとおりです👇
🩺 学習の進め方
この脳血管疾患シリーズは、
「5択クイズ編」と「要点解説編」 の2本立てになっています。
おすすめの使い方👇
💡 学習のポイント
📄 PDFダウンロード対応
印刷しての復習はもちろん、講師の方が授業資料や小テスト用としてもご利用いただけます。
PDFダウンロードボタンからどうぞ👇
✏️ 5択クイズに挑戦!脳血管疾患の理解度チェック
👇 いきなり問題を解くのが不安な人は、以下の要点解説記事へ
問1:くも膜下出血について、正しい記述はどれか。
- 硬膜とくも膜の間の出血である。
- 突然の激しい頭痛により発症する。
- CT検査で三日月型の血腫が確認できる。
- 髄液に血液は認められない。
- 一般的に予後良好である。
解答
正しい記述は、2 です。
解説
- 誤り:硬膜下ではなく、くも膜下腔の出血
くも膜下出血は、くも膜と軟膜の間(くも膜下腔)の出血です。 - 正しい:突然の激しい頭痛で発症
典型的には “雷鳴頭痛” と呼ばれる、急激で強い頭痛で発症します。
嘔吐や意識障害を伴うこともあります。 - 誤り:三日月型は硬膜下血腫
CTで三日月状に広がる血腫は 硬膜下血腫 の所見です。
くも膜下出血では、脳のすき間(脳溝など)に血液が広がります。 - 誤り:髄液には血液が混ざる
くも膜下腔には髄液が流れているため、出血すると 血性髄液 が確認されます。 - 誤り:一般に予後不良
再破裂や血管れん縮で悪化しやすく、死亡率・後遺症とも高い疾患です。
👉 くも膜下出血 については こちら で詳しく解説しています。
問2:脳出血について、正しい記述はどれか。
- 頭部外傷が原因である。
- 橋出血の頻度が最も高い。
- 睡眠中あるいは起床後まもなく起こる。
- 頭蓋内圧亢進症状がみられる。
- 脳圧亢進のある場合は、髄液検査により減圧をはかる。
解答
正しい記述は、4 です。
解説
- 誤り:脳出血の主な原因は高血圧
外傷で起きるのは、硬膜外血腫・硬膜下血腫 などです。
脳出血は 細い動脈が破れる“高血圧性”出血 が最多です。 - 誤り:最も多いのは被殻出血
橋(脳幹)出血はとても重症ですが、頻度は低め。
脳出血で多いのは 被殻 → 視床 の順です。 - 誤り:睡眠中・起床後は脳梗塞に多い
特にアテローム血栓性脳梗塞がこの発症パターンです。
脳出血は 日中活動時の発症が多い とされます。 - 正しい:頭蓋内圧亢進症状がみられる
出血で脳が圧迫されるため、頭痛・嘔吐・意識障害 などがみられます。 - 誤り:脳圧が高いときは髄液検査は禁忌
腰椎穿刺で髄液を抜くと、脳ヘルニア を起こす危険があります。
脳出血が疑われる場合は まずCT を行います。
👉 脳出血 については こちら で詳しく解説しています。
問3:脳出血について、正しい記述はどれか。
- 皮質下出血は、脳出血の中で最も予後が悪い。
- 被殻出血では、健側をにらむ共同偏視がみられる。
- 橋出血では、回転性めまいがみられる。
- 小脳出血では、四肢麻痺による起立・歩行障害がみられる。
- 視床出血では、感覚障害がみられる。
解答
正しい記述は、5 です。
解説
- 誤り:最も予後不良なのは橋(脳幹)出血
皮質下出血(大脳皮質近く)は比較的予後が良く、予後が最も悪いのは橋出血 です。 - 誤り:被殻出血では「患側をにらむ」共同偏視
被殻出血では、大脳基底核の障害により眼球が出血側(患側)へ向く 共同偏視がみられます。
「健側をにらむ」共同偏視は小脳出血でみられます。 - 誤り:回転性めまいは小脳出血で出現
小脳は平衡機能に関与するため、小脳出血では回転性のめまいが出現します。 - 誤り:小脳出血の歩行障害は“失調”によるもの
四肢麻痺ではなく、体のバランスが取れない(小脳失調) ために起立・歩行障害が起こります。 - 正しい:視床出血では感覚障害が出現
視床は 感覚の中継点 であるため、出血すると、しびれ・感覚低下・感覚の異常感(ジンジン・ピリピリ)がみられます。
👉 脳出血 については こちら で詳しく解説しています。
問4:ラクナ梗塞について、正しい記述はどれか。
- 他の部位からの血栓や脂肪などが血流に乗って脳血管を塞ぐために生じる。
- 広範な脳領域が障害を受ける。
- 脳梗塞のうち、最も重症である。
- 前駆症状がみられる。
- 意識障害や失語症はみられない。
解答
正しい記述は、5 です。
解説
- 誤り:塞栓(心原性)ではなく“細い動脈の閉塞”
ラクナ梗塞は、脳の細い動脈(穿通枝)が詰まることで起こります。
血栓が飛んでくるタイプ(心原性脳塞栓症)とは異なります。 - 誤り:障害される範囲は“小さく限局”
ラクナ(lacune=小さなくぼみ)の名前のとおり、病変は 小範囲 です。
広範な障害はアテローム血栓性や心原性でみられます。 - 誤り:最重症は心原性脳塞栓症
ラクナ梗塞は比較的軽症例が多く、脳梗塞の中で最も重症ではありません。 - 誤り:前駆症状(TIA)はアテローム血栓性で多い
ラクナ梗塞では 前駆症状はあまりみられない のが普通です。 - 正しい:意識障害や失語は出にくい
病変が小さいため、意識障害・失語などの高度な症状は生じにくい のが特徴です(軽い片麻痺・しびれなどで見つかることが多い)。
👉 ラクナ梗塞 については こちら で詳しく解説しています。
問5:脳塞栓について、正しい記述はどれか。
- 原因のほとんどが、脳動脈瘤破裂によるものである。
- 僧帽弁狭窄症に続発する例が最も多い。
- 症状の悪化と改善を繰り返し、徐々に進行する。
- 後大脳動脈の塞栓では、視覚障害を起こすことが多い。
- 予後は一般に良好である。
解答
正しい記述は、4 です。
解説
- 誤り:脳動脈瘤破裂は“くも膜下出血”の原因
脳塞栓は、心臓でできた血栓が脳へ飛んで詰まる疾患です。 - 誤り:脳塞栓は“心房細動”に続発する例が最多
僧帽弁狭窄症でも心房細動が起こりやすく塞栓の原因になりますが、脳塞栓の原因として 最も多いのは心房細動 です。 - 誤り:脳塞栓は“突発完成型”
脳塞栓は血栓が突然詰まるため、症状が一気に完成する“突発完成型” です。
悪化と改善を繰り返すのはアテローム血栓性に多くみられます。 - 正しい:後大脳動脈の塞栓では視覚障害が多い
後大脳動脈(PCA)は 後頭葉(視覚野) を栄養しているため、塞栓が起こると 半盲などの視覚障害 がよくみられます。 - 誤り:予後不良例が多い
脳塞栓は広い範囲が一度に障害されやすく、重症で予後不良になりやすい脳梗塞 です。
👉 脳塞栓 については こちら で詳しく解説しています。
問6:脳血管疾患について、正しい記述はどれか。
- くも膜下出血では、多くの場合、発症以前に頭痛やめまいを訴える。
- 脳出血では、髄液検査でキサントクロミーが確認される。
- 脳梗塞の急性期は、必ず降圧薬を投与する。
- アテローム血栓性脳梗塞は、日中活動時に発症する。
- もやもや病は、くも膜下出血の原因となる。
解答
正しい記述は、5 です。
解説
- 前駆症状がみられるのは“アテローム血栓性脳梗塞”
アテローム血栓性脳梗塞では、前駆症状(一過性脳虚血発作)がみられることがあります。
くも膜下出血の多くは、急激で強い頭痛で発症します。 - 誤り:キサントクロミーは“くも膜下出血”でみられる
脳出血(脳内出血)では髄液は汚れにくい部位です。
髄液が黄色調になるキサントクロミーは くも膜下出血 の所見です。 - 誤り:脳梗塞急性期は“むやみに降圧しない”
急に血圧を下げると、脳の血流がさらに低下するため危険です。
状況に応じて慎重に管理しますが、必ず降圧薬を使うわけではありません。 - 誤り:日中発症が多いのは“脳出血”や“心原性脳塞栓症”
アテローム血栓性脳梗塞は睡眠中・起床後 に悪化しやすいタイプです。 - 正しい:もやもや病はくも膜下出血の原因になりうる
もやもや病では脳底部の血管が脆くなり、脳動脈瘤や出血(くも膜下出血) を起こすことがあります。
👉 脳血管疾患 については こちら で詳しく解説しています。
問7:硬膜下血腫について、正しい記述はどれか。
- 原因では動脈硬化が最も多い。
- 脳実質内の出血がみられる。
- 症状は発症直後から出現することが多い。
- 慢性型では認知症様症状がみられる。
- 髄液に血液が混入する。
解答
正しい記述は、4 です。
解説
- 誤り:主な原因は“頭部外傷”
特に高齢者では軽い頭部打撲でも架橋静脈が切れやすく、外傷が原因となることが多いです。 - 誤り:脳実質内の出血は“脳出血”
硬膜下血腫は 脳の外側(硬膜とくも膜の間) に血液がたまる状態です。 - 誤り:ゆっくり進行する慢性型が多い
重症外傷では発症直後から症状が出る急性型となりますが、硬膜下血腫の多くは、数週間〜数ヶ月かけて症状が出現する慢性型です。 - 正しい:慢性型では認知症様症状が多い
ゆっくり進行するため、物忘れ・ぼんやりする・歩行がふらつくなど、認知症に似た症状 が出ることがあります。 - 誤り:血性髄液はくも膜下出血でみられる
硬膜下血腫では、くも膜の外側(硬膜下腔)に血液が貯留します。
髄液のあるくも膜下腔ではないので、血性髄液はみられません。
👉 硬膜下血腫 については こちら で詳しく解説しています。
📄 記事の問題をPDFでダウンロードできます!
この記事の5択クイズを、印刷しやすいPDFにまとめました。
“cerebrovascular-disease” をダウンロード cerebrovascular-disease-1.pdf – 121 回のダウンロード – 443.46 KB🔍 クイズが解けなかった人へ
👇 以下の要点解説記事をしっかり読んでから、再トライしてみてください。
🔗 循環器疾患の学習に役立つ関連記事
👇 循環器系の基本的な解剖生理を復習したい人はこちら
👇 循環器疾患の 5択クイズの記事一覧 はこちら
👇 循環器疾患の 図解つき要点解説の記事一覧 はこちら
👇 循環器疾患の 総合演習 はこちらから挑戦できます!
👇 循環器疾患の 頻出問題だけ 短時間で復習したい方はこちら
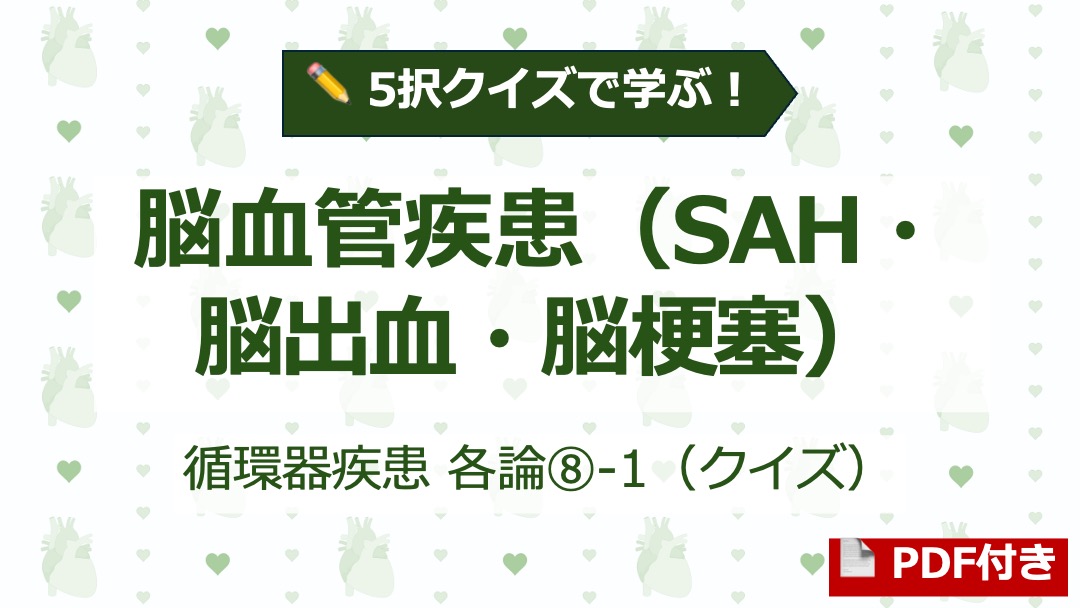
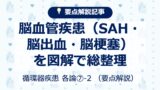

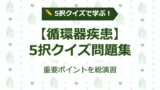
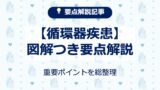
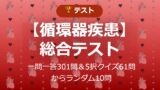

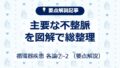
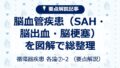
コメント