ウイルス性肝炎は、国家試験でも頻出のテーマであり、ウイルスのタイプごとの違いがよく出題されます。また、HIV感染症は、結核・マラリアと並ぶ「世界三大感染症」の一つで、現在も多くの感染者が存在する重要な疾患です。試験対策としても、しっかり押さえておきたいポイントが多数あります。
この記事では、これらの主要な疾患に加え、SARSやMERSなどのコロナウイルス感染症(※新型コロナは除く)、小児に多い流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、「キス病」とも呼ばれる伝染性単核球症、そしてHIVと関係の深いサイトメガロウイルス病を取り上げ、計6疾患について学びます。
最初に5択問題が7問出てきます。
授業で一度習った内容の確認や、試験直前の総チェックとして活用したい方、または「どんな点が問われやすいのか」を把握したい方は、さっそくクイズにチャレンジしてみましょう!
「いきなり問題はちょっと不安…」という方は、後半の
📚 感染症まとめ|クイズで登場した疾患を再チェック!
で各疾患の要点を確認してから挑戦するのがおすすめです。
📝 本記事に掲載している5択クイズは、PDFでもダウンロード可能です。
印刷して復習したい方は、ダウンロードボタンからご利用ください。
また、講師の方は授業資料としての活用もおすすめです。
学生の理解を助ける補助教材として、お役立ていただけます。
💡感染症の全体像をまとめて確認したい方は、以下のまとめ記事もご活用ください:
👉【保存版】感染症クイズ&解説記事一覧|覚えにくい感染症を一気に攻略!
🖊️ クイズで学ぶ|そのウイルス感染症②
問1:ウイルス性肝炎について正しいのはどれか。
- A型肝炎は、高率で再発する。
- A型肝炎は、慢性化しやすい。
- B型肝炎は、生ガキの経口摂取で感染する。
- B型肝炎は、持続感染(キャリア化)することはない。
- C型肝炎ウイルスは、刺青や鍼治療でも感染することがある。
解答
正しい記述は、5 です。
解説
- A型肝炎に感染すると体内で抗体が産生され終生免疫を獲得するため、再発することは稀です。
- A型肝炎の多くは一過性で、慢性化することはありません。
- B型肝炎ではなく、A型肝炎の特徴です。B型肝炎は血液感染、性感染、母子感染しますが、経口感染はありません。
- B型肝炎は一過性感染(急性肝炎)と持続感染(慢性化、キャリア化)があります。特に乳児期感染では90%以上が持続感染します。
- 正しい記述です。C型肝炎は、主に血液感染します。母子感染や性感染もありますが、感染率は低いです。覚醒剤など注射器の回し打ちや消毒が十分でないピアスの穴あけなどもリスクとなります。
問2:ウイルス性肝炎について、正しいのはどれか。
- A型肝炎は、最も劇症化しやすい。
- A型肝炎は、主に性的接触感染する。
- B型肝炎には、予防ワクチンがない。
- C型肝炎の原因は、現在ではほとんどが輸血によるものである。
- 慢性ウイルス性肝炎の初期には、ほとんど自覚症状がみられない。
解答
正しい記述は、5 です。
解説
- 最も劇症化しやすいのは、B型肝炎です。劇症化率は約1%ですが、その場合の致死率は高くなります。
- A型肝炎は、主に生牡蠣など汚染された食品や水の経口感染により発症します。
- A型肝炎、B型肝炎には予防ワクチンがありますが、C型肝炎には現在予防ワクチンはありません。A型肝炎は任意接種、B型肝炎は定期接種です。
- 輸血によって感染するウイルスには、HBV、HCV、HIVなどがあります。現在、国内の血液製剤についてはウイルス検査を実施しているため、C型肝炎に限らず、輸血による血液感染はほとんどありません。
- 正しい記述です。慢性肝炎では、初期症状がほとんどないため、症状に気づく頃にはかなり進行していることもあります。
問3:ウイルス性肝炎について、正しいのはどれか。
- 急性ウイルス性肝炎は、EBウイルス、サイトメガロウイルスなどでも発症する。
- A型肝炎は、夏期に好発する。
- A型・B型肝炎ウイルスは、血液を介して感染する。
- C型肝炎ウイルスの主要な感染経路は、母子感染である。
- C型・E型肝炎ウイルスには、予防ワクチンがある。
解答
正しい記述は、1 です。
解説
- 正しい記述です。急性ウイルス性肝炎の原因の多くは、A〜E型肝炎ウイルスですが、EBウイルスやサイトメガロウイルスも原因として知られています。
- A型肝炎は、冬から春にかけて好発します。
- B型肝炎ウイルスは血液を介して感染しますが、A型肝炎ウイルスは経口感染します。
- C型肝炎ウイルスは母子感染を起こすこともありますが、稀です。主な感染経路は血液感染です。
- 現在、国内で承認されているC型肝炎ワクチン、E型肝炎ワクチンはありません。
問4:ヒト免疫不全ウイルスについて、正しいのはどれか。
- アデノウイルスの一種である。
- RNAウイルスに分類される。
- AIDSと略される。
- 鼻汁、唾液、涙を介して感染する。
- 血液感染しない。
解答
正しい記述は、2 です。
解説
- ヒト免疫不全ウイルスは遺伝子としてRNAを持つRNAウイルスで、ウイルスが持つ逆転写酵素によりRNAからDNAを作り出すレトロウイルスの一種です。ヒトの細胞がDNAからRNAを作り出すのと逆になります(retro- とは、「後ろに」や「逆の」といった意味があります)。
- 上記を参照してください。
- AIDSは後天性免疫不全症候群(acquired immunodeficiency syndrome)のことで、ヒト免疫不全フイルスは、HIV(human immunodeficiency virus)と略します。HIVの感染によりAIDSが引き起こされます。
- HIVは、体液や血液中で生息しますが、空気や水の中では感染力をなくしてしまいます。したがって、鼻汁や唾液、涙は感染源とはなりません。
- HIVは、血液感染、性感染、母子感染します。
問5:伝染性単核球症について、正しいのはどれか。
- 人畜共通感染症である。
- パピローマウイルスの感染によって起こる。
- 単核球と呼ばれる異型顆粒球の数が増える。
- 初感染が青春期に起こった場合に症状が現れることが多い。
- 致命率が高く、予後不良である。
解答
正しい記述は、4 です。
解説
- 人畜共通感染症ではありません。
- 伝染性単核球症の原因は主にEBウイルスで、唾液を介して感染するので kissing desease とも呼ばれます。
- 単核球と呼ばれる異型リンパ球の増加がみられます。
- 正しい記述です。
- 予後良好で、2−3週間で自然治癒します。
問6:正しいのはどれか。
- ヒト免疫不全ウイルス感染から後天性免疫不全症候群までの期間は、1年である。
- SARSとMERSは、ともに3類感染症である。
- サイトメガロウイルス病は、胎盤や産道を介して垂直感染する。
- 流行性耳下腺炎は、EBウイルスの感染症である。
- 急性E型肝炎は、経口感染しない。
解答
正しい記述は、3 です。
解説
- ヒト免疫不全ウイルスの感染から後天性免疫不全症候群の発症までの期間は、数年〜十数年です。
- 重症急性呼吸器症候群(SARS)と中東呼吸器症候群(MERS)は、ともに2類感染症に指定されています。
- 正しい記述です。母乳や唾液、尿、血液などから子供の時に感染することが多いです。その他、性感染もあります。ただし、健康な子供や成人が感染してもほとんど症状は出ません。
- 流行性耳下腺炎は、ムンプスウイルスの感染症です。EBウイルスは、伝染性単核球症や上咽頭癌などの原因となります。
- 急性E型肝炎は経口感染します。病原体であるE型肝炎ウイルスは、ブタやイノシシ、シカなどが保有しており、これらの動物の生食や加熱不十分な調理が原因となります。
問7:正しいのはどれか。
- HIVに感染すると数週間後に抗体産生があり、ウイルスと抗体は終生持続する。
- 現在、ヒト免疫不全ウイルスに対するワクチンが実用化されている。
- ニューモシスチス肺炎は、健常な若年者が発症することが多い。
- サイトメガロウイルス病は、一般に「おたふくかぜ」とよばれる。
- 流行性耳下腺炎(ムンプス)のワクチンは、定期接種である。
解答
正しい記述は、1 です。
解説
- 正しい記述です。HIV感染後、通常2〜8週間で抗体が産生され、以後、HIVと抗体はどちらも体内に持続します。ただし、抗体が存在していてもウイルスの排除はできず、感染は持続します。
- 現在、HIVに対するワクチンは存在しません。
- ニューモシスチス肺炎は、AIDS患者など免疫低下患者に好発します。
- 「おたふくかぜ」は、流行性耳下腺炎の俗称です。
- 流行性耳下腺炎のワクチンは任意接種で、定期接種には含まれていません(2025年時点)。
📚 感染症まとめ|クイズで登場した疾患を再チェック!
急性ウイルス性肝炎
- 肝炎ウイルスの感染による急性肝炎です。
- A〜E型肝炎ウイルスによるものがほとんどを占めますが、EBウイルスやサイトメガロウイルスも原因となります。
- ウイルスの型によらず類似した症状が出ますが、一部の型(例:E型肝炎の妊婦など)では重症化しやすい例もあります。
- 全身倦怠感や、食欲不振、悪心、嘔吐、発熱、筋肉痛などのインフルエンザ様症状が出現し、その後、黄疸や皮膚掻痒感、肝腫大などがみられます。
- 血液検査では、AST、ALT、ビリルビンの上昇が認められます。
- 自然治癒が多いため、保存的治療を行います。
A型急性肝炎
- RNAウイルスであるA型肝炎ウイルス(HAV)の経口感染が原因となります。
- 原因食品として生の牡蠣などがあり、冬から春にかけて好発します。
- 2~6週程度の潜伏期を経て発症しますが、一過性感染で、慢性化することはほとんどありません。
- IgM型HA抗体の検出、TTT(チモール混濁試験)、ASTやALTの上昇などから診断されます。
- 安静を保ち、消化の良い栄養を摂取して肝機能の回復を促します。特別な治療は不要で、自然治癒が期待されます。
B型急性肝炎
- DNAウイルスであるB型肝炎ウイルス(HBV)の血液感染、垂直感染(母子感染)、性行為感染が原因となります。
- 潜伏期は1~6ヶ月間で、一過性(急性肝炎)および持続感染(慢性化、キャリア化)します。
- 乳児期などに感染して無症候性キャリアとなった場合、後年に慢性肝炎へと進展することがあります。
- 劇症肝炎の原因として、最多(約40%)です。
- HBVが持つ各種抗原と、それに対する抗体の検出やASTやALTの上昇などから診断されます。
C型急性肝炎
- RNAウイルスであるC型肝炎ウイルス(HCV)の主に血液感染が原因となります。
- 慢性化率が高く(40~70%)、放置すると肝硬変や肝細胞癌に移行します。
- HCV抗体等の検出やAST、ALTの上昇などから診断されます。
- 現在、実用化されている予防ワクチンはありません。
- かつてはインターフェロン療法が主流でしたが、現在はインターフェロンを用いない直接作用型抗ウイルス薬(DAAs)による治療が主流となっています。
慢性肝炎
- 急性肝炎罹患後、6ヶ月以上肝臓に炎症が持続するものをいいます。
- 原因の多くはB型肝炎ウイルス(HBV)またはC型肝炎ウイルス(HCV)感染によるもので、特に日本ではHCVが主因となってきました。 近年では治療の進歩によりHCV感染による慢性肝炎は減少傾向にあります。その他の原因として、アルコールや薬剤があります。
- 自覚症状はほとんどなく、放置すると肝硬変や肝細胞癌へ移行します。
- 血清アルブミン値の低下や血清グロブリン値の上昇がみられます。
- 各種抗原・抗体等の検出やAST、ALTの上昇などから診断されます。
- かつてはインターフェロン療法が主流でしたが、現在では直接作用型抗ウイルス薬(DAAs)によるインターフェロンを使用しない治療(インターフェロンフリー治療)が中心となっています(特にHCVに対して)。
- 抗ウイルス作用はありませんが、肝炎を鎮静化して、病気の進行を抑える目的で肝庇護療法が行われます。
- 肝庇護療法では、肝機能を改善・安定化させる目的でグリチルリチン製剤(抗炎症・肝細胞保護作用)や、胆汁の流れを改善するウルソデオキシコール酸(UDCA)などが用いられます。
ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病
- HIV(ヒト免疫不全ウイルス)の性行為、血液(注射器の共有など)、母子(胎内・分娩時・授乳)感染が原因となります。
- HIVが体内に侵入すると、CD4陽性T細胞に感染し、破壊していきます。
- 数年~十数年の無症候期が続いた後に、発熱、体重減少、下痢、リンパ節腫脹などの症状が出現し、次第に日和見感染症(ニューモシスチス肺炎、サイトメガロウイルス感染症、カンジダ症など)、悪性腫瘍、HIV脳症などを発症します。
- 現在では、多剤併用療法(ART:抗レトロウイルス療法、以前はHAARTと呼ばれていました)が主流であり、HIVの増殖を強力に抑制できますが、HIVを完全に排除(根治)する治療法は、2025年現在も確立されておらず、生涯にわたる治療継続が基本です。
サイトメガロウイルス病
- サイトメガロウイルス(CMV)は、ヒトヘルペスウイルス5型(HHV-5)に分類され、胎盤・産道・母乳を介する垂直感染や、免疫低下状態での後天性感染によって発症します。
- 健康な成人では多くが不顕性感染で終わりますが、免疫不全患者(例:AIDS、臓器移植後、がん化学療法中)では、肺炎・肝炎・消化管病変・網膜炎などの重篤な症状を引き起こすことがあります。
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- ムンプスウイルスの飛沫または直接感染が原因となります。
- 幼児期(5~10歳)に好発し、発熱、耳下腺の腫脹・疼痛などを引き起こします。
- 耳下腺の腫脹や疼痛は、片側性に発症しても数日後には両側性になることが多いです。
- 合併症として、無菌性髄膜炎(小児の最多合併症)や難聴、膵炎などがあります。
- 思春期以降に感染した場合、男性では精巣炎、女性では卵巣炎を合併することがあります。
- 対症療法のみですが、予防には生ワクチンがあります(任意接種)。
伝染性単核球症
- EBウイルス(ヒトヘルペスウイルス4型:HHV-4)がB細胞に感染し、それを排除しようとするT細胞の免疫反応により症状が出現する疾患です。
- 一般に唾液を介して感染するため、kissing disease とも呼ばれます。
- 3歳までに感染すると不顕性感染が多いですが、思春期に感染すると症状が現れやすくなります。
- 症状として、弛張熱(38℃以上)、全身リンパ節腫大(特に頸部)、咽頭痛(扁桃炎)、ときに発疹(皮膚、口蓋の紅斑)、肝脾腫などがみられます。
- かつてはポール・バンネル反応が診断に用いられていましたが、現在ではEBウイルス抗体検査(VCA-IgMやEBNA)が用いられます。
- 血液検査では、末梢血中の異型リンパ球の上昇が特徴的です。
- EBウイルスに対する治療薬はありませんが、自然治癒傾向が高く、予後良好な疾患です。
コロナウイルス感染症
- ヒトに蔓延している風邪のウイルス4種類と、動物から感染する重症肺炎ウイルス(SARS、MERS)が知られています。
- SARSは重症急性呼吸器症候群(Severe Acute Respiratory Syndrome)のことで、2002年中国広東省で発生し周辺の国々に拡大しましたが、2003年7月に終息しました。
- MERSは中東呼吸器症候群(Middle East Respiratory Syndrome)のことで、ヒトコブラクダが保有するコロナウイルスの一種がヒトに感染したと考えられています。2012年、アラビア半島とその周辺地域で発生しました。
📄 記事の問題をPDFでダウンロードできます!
この記事の5択クイズを、印刷しやすいPDFにまとめました。
“virus_infection_2_quiz” をダウンロード virus_infection_2_quiz.pdf – 228 回のダウンロード – 622.94 KB✏️ クイズ形式で覚えたい人はこちら
この記事と真菌感染症 の記事まで勉強が終わった人は、クイズで理解度をチェックしてみてください。
一問一答形式で選択肢一つ一つをじっくり復習できるクイズと5択クイズでサクッと復習できるクイズの2種類を用意しています。
真菌感染症の記事はこちら👇
🔗 その他の感染症の記事はこちら
感染症に関する復習用記事を、テーマごとに分けてまとめています。
それぞれの記事では、5択クイズ+要点解説で重要ポイントをしっかり押さえられます。
苦手な分野や気になるテーマを重点的に確認したい方はこちらから👇
🔗【病原体の種類】5択クイズで理解!細菌・ウイルス・真菌・寄生虫の違いを整理しよう
🔗【感染症の基本】5択クイズで確認!日和見感染・感染経路・血液所見・ワクチンを理解しよう
🔗【感染症の分類】5択クイズで覚える!感染症法で定められた1〜5類感染症
🔗【抗酸菌】5択クイズで覚える!結核・ハンセン病・非結核性抗酸菌症
🔗【人獣共通感染症(人畜共通感染症)】5択クイズで覚える!ペスト・炭疽・ブルセラ症・野兎病・リステリア症
🔗【その他の細菌感染症①】5択クイズで理解!ジフテリア・百日咳・破傷風
🔗【その他の細菌感染症②】5択クイズで理解!猩紅熱・髄膜炎・レジオネラなど6疾患
🔗【性感染症】5択クイズで覚える|梅毒・淋病・クラミジア・トリコモナス・軟性下疳
🔗【スピロヘータ・クラミジア・リケッチア】5択クイズで覚える|重要7疾患
🔗【中枢神経系の感染症とCJD】5択クイズで総復習!ポリオ・日本脳炎など7疾患
🔗【その他のウイルス感染症①】5択クイズで覚える|デング・ラッサ熱・ヘルペス・麻疹など9疾患
🔗【寄生虫感染症】5択クイズで理解!マラリア・アニサキス・エキノコックスなど全12疾患を一気に確認!
🖊️ 5分で復習できるクイズ記事はこちら
苦手な分野がはっきりしている方は、まずテーマごとのクイズで集中的に復習してから、総合問題に進むのがおすすめです。
以下のクイズでは、総論・細菌・ウイルス・真菌・寄生虫などの感染症を分野別にチェックできます。
1テーマあたり短時間で解けるので、空いた時間に少しずつ取り組めます。
👇 気になる分野から、ぜひチャレンジしてみてください。
🔗【5分で復習】感染症①|病原体・基本・分類をクイズでチェック!
🔗【5分で復習】感染症②|食中毒・抗酸菌感染症をクイズでチェック!
🔗【5分で復習】感染症③|人獣共通感染症・その他の細菌感染症
🔗【5分で復習】感染症④|スピロヘータ・クラミジア・リケッチア・性感染症
🔗【5分で復習】感染症⑤|ポリオ・デング熱・ヘルペスなど多彩なウイルス感染症をクイズで確認!
🔗【5分で復習】感染症⑦|覚えにくい寄生虫感染症をクイズで確認!
👇 総合問題はこちらからチャレンジ!
🔗【感染症クイズ総まとめ】一問一答&5択で300問以上に挑戦!隙間時間で基礎力アップ!
📚 感染症全体の一覧や分類を一度に整理したい方は、こちらの記事もどうぞ:
👉【保存版】感染症クイズ&解説記事一覧|覚えにくい感染症を一気に攻略!

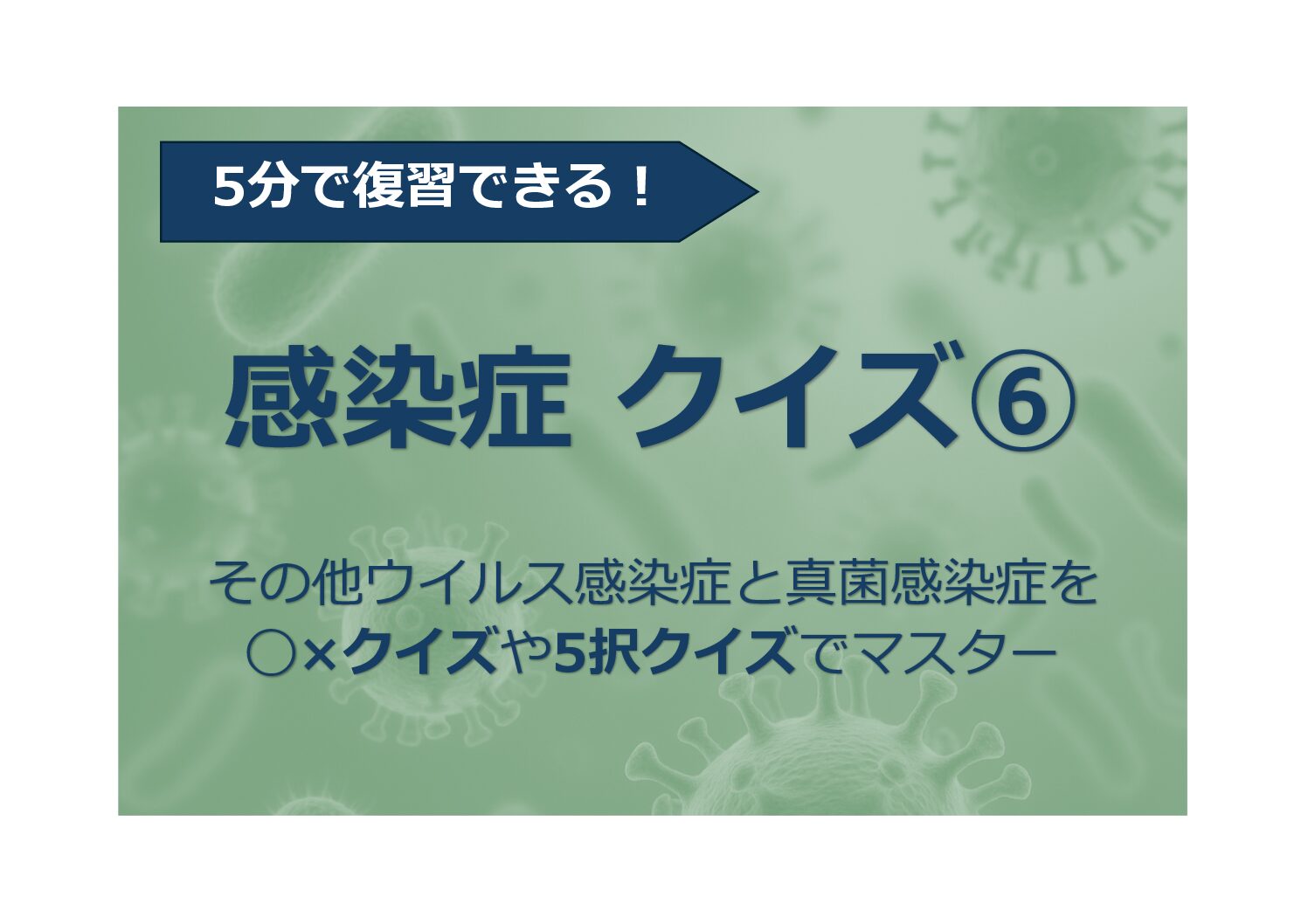

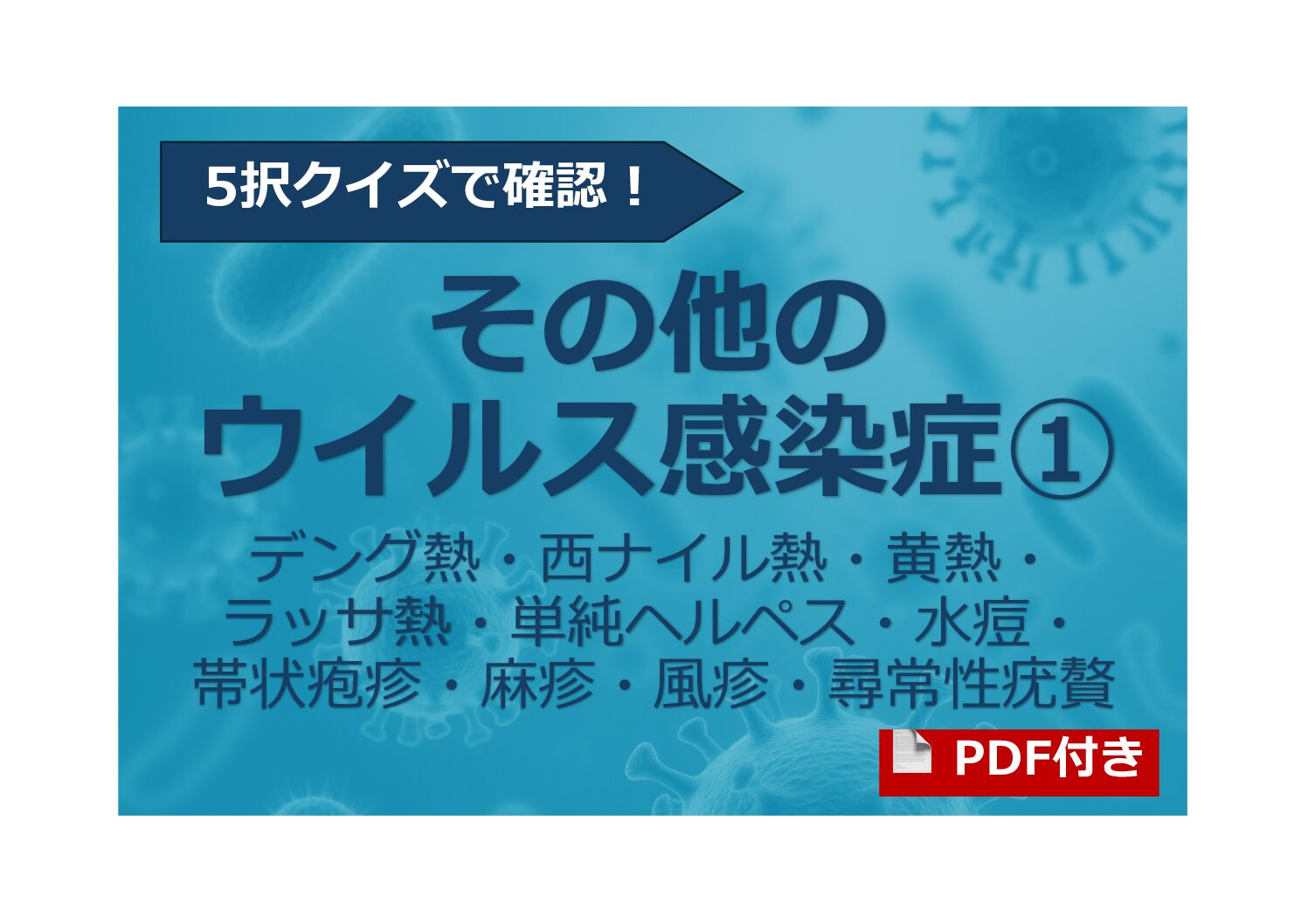
コメント