寄生虫は、「原虫」と「蠕虫」に分類され、細菌やウイルス、真菌とは異なる性質をもつ病原体です。
(詳しくは👉 病原体の種類を解説した記事 で復習しましょう)
国内ではあまり見られない感染症も多いため、感染症分野の中でもとくに覚えにくいテーマのひとつだと思います。
この記事では、
マラリア・トキソプラズマ症・回虫症・レフレル症候群(Löffler症候群)・アニサキス症・フィラリア症・住血吸虫症・肝吸虫症・肺吸虫症・日本海裂頭条虫症・無鈎条虫症・包虫症(エキノコックス症)
といった代表的な寄生虫感染症12疾患を取り上げ、
医療系の資格試験や国家試験対策にも役立つ5択クイズ形式で重要ポイントを整理しています。
実際に問題を解きながら学ぶことで、記憶に残りやすく、理解も深まります。
📝 本記事に掲載している5択クイズは、PDFでもダウンロード可能です。
印刷して復習したい方は、ダウンロードボタンからご利用ください。
また、講師の方は授業資料としての活用もおすすめです。
学生の理解を助ける補助教材として、お役立ていただけます。
💡感染症の全体像をまとめて確認したい方は、以下のまとめ記事もご活用ください:
👉【保存版】感染症クイズ&解説記事一覧|覚えにくい感染症を一気に攻略!
👍 おすすめの使い方
🖊️ クイズで学ぶ|寄生虫感染症
問1:原虫に関して、正しい記述はどれか。
- 単細胞の原核生物である。
- 細菌と同じく、細胞壁を持つ。
- 全て経気道的に感染する。
- マラリアの病原体は、原虫の一種である。
- 線虫、条虫、吸虫類に分類される。
解答
正しい記述は、4 です。
解説
- 原虫は単細胞の真核生物(核膜を持つ生物)で、原核生物である細菌とは異なります。
- 原虫は細菌とは異なり、細胞壁は持ちません。
- 原虫の感染経路はさまざまで、経口感染や昆虫(蚊など)による媒介が代表的です。経気道感染は一般的ではありません。
- 正しい記述です。
マラリアの病原体であるPlasmodium属(プラスモディウム属)は、原虫の一種です。 - 線虫、条虫、吸虫類は、いずれも蠕虫に分類される多細胞の寄生虫であり、原虫ではありません。
問2:寄生虫感染症について、正しい記述はどれか。
- マラリアは、蚊によって媒介される。
- トキソプラズマ症は、真菌感染症である。
- 回虫症は、シラミによって媒介される。
- アニサキスは、俗にサナダムシとも呼ばれる。
- エキノコックス症は、ネコとの接触が原因となる。
解答
正しい記述は、1 です。
解説
- 正しい記述です。マラリアは、ハマダラ蚊(雌)によって媒介される原虫感染症です。
- トキソプラズマ症は、トキソプラズマ・ゴンディ(Toxoplasma gondii)という原虫によって引き起こされる疾患です。真菌感染症ではありません。
- 回虫症は、感染した人の糞便中に排泄された回虫卵が土壌中で成熟し、成熟卵を経口摂取することで感染が成立します。
- アニサキスは線虫であり、サナダムシ(条虫)とは異なります。サナダムシとは一般的に「有鉤条虫」「無鉤条虫」「日本海裂頭条虫」などを指します。
- エキノコックス症(包虫症)は、主にイヌ科の動物(イヌやキツネなど)が最終宿主となる寄生虫感染症です。ネコではなく、イヌ科動物の糞便に含まれる虫卵を経口摂取することでヒトに感染します。
問3:寄生虫感染症について、正しい記述はどれか。
- マラリア原虫は、脾臓内で増殖する。
- トキソプラズマ症では、間欠熱や貧血、脾腫がみられる。
- 回虫症は、レフレル症候群の原因となる。
- アニサキス症では、象皮病がみられる。
- エキノコックス症では、潜伏期が比較的短いのが特徴である。
解答
正しい記述は、3 です。
解説
- マラリア原虫は、ハマダラ蚊の刺咬によりヒト体内に侵入すると肝細胞内で増殖し、その後赤血球内で増殖します。マラリアでは脾腫がみられますが、脾臓は増殖の場となりません。
- 間欠熱や貧血、脾腫は、マラリアでみられる特徴的な所見です。後天性トキソプラズマ症は、健康な成人が感染しても軽症が無症状のことが多いですが、一部でリンパ節腫脹や軽度の発熱、倦怠感、筋肉痛などがみられます。免疫低下時には、重症化することもあります。
- 正しい記述です。ヒト回虫の幼虫が肺を移行する際、一過性の肺浸潤や好酸球増多を伴うレフレル症候群を引き起こすことがあります。
- 象皮病は、フィラリア症でみられる症状です。アニサキス症では、激しい腹痛などの急性腹症様症状がみられます。
- エキノコックス症は、肝臓や肺などの臓器に包虫嚢胞が形成されるまで長い潜伏期(数年~十数年)を経ることが多いのが特徴です。
問4:寄生虫感染症について、正しい記述はどれか。
- マラリアには、予防ワクチンが存在しない。
- トキソプラズマ症では、不顕性感染はほとんどない。
- アニサキス症は、蚊によって媒介される。
- 無鈎条虫症は、サケやマスの生食が原因となる。
- 肝ジストマ症は、コイ科の淡水魚の生食で感染する。
解答
正しい記述は、5 です。
解説
- マラリアに対する予防ワクチンは存在し、アフリカ地域を中心に接種が行われています。
- トキソプラズマ症は、感染者の約70~80%が無症状または軽症で経過します。重症化は免疫低下時や胎児感染などでみられます。
- アニサキスは、サバ、アジ、イカなどの魚介類を中間宿主とするため、魚介類の生食で感染します。
- 無鈎条虫症は主に牛肉の生食や不十分な加熱によって感染します。サケやマスの生食は、日本海裂頭条虫による感染の主な原因とされます。
- 正しい記述です。肝ジストマ症(肝吸虫症)は、コイ科の淡水魚を生食することで感染し、虫体は肝胆道系に寄生します。
問5:寄生虫感染症について、正しい記述はどれか。
- トキソプラズマ症は、免疫低下患者に好発する。
- 回虫症では、乳糜尿や陰嚢水腫がみられる。
- 肝吸虫症は、イノシシ肉の生食が原因となる。
- アニサキス症では、激しい痒みを伴う皮疹が現れる。
- エキノコックス症は、糸状虫が蚊によって媒介されて発症する。
解答
正しい記述は、1 です。
解説
- 健常者が感染しても無症状または軽症ですむことが多いですが、AIDS患者やステロイド治療などで免疫低下状態の患者では、脳症や網脈絡膜炎などの重症化がみられます。
- 回虫症では、回虫が肺を経由する移行期には呼吸器症状を、腸管内で大量寄生すれば消化器症状を引き起こします。一方、乳糜尿や陰嚢水腫は、主にフィラリア症でみられる症状です。
- 肝吸虫症(肝ジストマ症)の主な感染経路は、淡水魚(コイやフナなど)の生食・加熱不十分な摂食によるものです。一方、イノシシ肉の生食は、近年、肺吸虫症のリスクとして報告されています。
- アニサキス症の主症状は、急性腹痛、悪心・嘔吐などの消化器症状です。
- エキノコックスはキツネなどのイヌ科の動物を最終宿主とするため、それらの糞便中に排泄された虫卵により土壌などが汚染され、経口的にヒトに感染します。糸状虫が蚊によって媒介されて発症するのは、フィラリア症です。
問6:正しいのはどれか。
- トキソプラズマは、胎盤を介して胎児に感染する。
- 住血吸虫は、ハマダラ蚊によって媒介される。
- 肝吸虫症では、寄生虫が門脈系で産卵して虫卵による血管閉塞を起こす。
- フィラリア症では、胆管炎・胆嚢炎を繰り返す。
- 日本海裂頭条虫症では、不顕性感染は少ない。
解答
正しい記述は、1 です。
解説
- 妊婦が初感染した場合に胎盤を介して胎児へ伝播して、先天性トキソプラズマ症を引き起こすことがあります。流産・死産となったり、先天性障害(脳内石灰化、水頭症、網脈絡膜炎など)を引き起こすリスクがあるため、妊娠中の初感染には注意が必要です。
- 住血吸虫は淡水に生息する巻貝が中間宿主となり、その水中を泳ぐセルカリアという幼虫が皮膚を貫通して感染します。一方、ハマダラ蚊はマラリア原虫を媒介します。
- 肝吸虫は、淡水魚(コイやフナなど)の生食によって感染し、胆管内に寄生することで胆管炎や胆石形成、慢性化すると胆道癌のリスクを増加させます。門脈系で産卵し、虫卵による血管閉塞を起こすのは、住血吸虫です。
- フィラリア症 は、糸状虫(バンクロフト糸状虫など)が蚊によって媒介され、リンパ管に寄生して、リンパ浮腫(象皮病)や陰嚢水腫、乳糜尿などを引き起こします。
- 日本海裂頭条虫は俗に「サナダムシ」と呼ばれる条虫の一種で、サケやマスなどの生食で感染します。感染しても無症状で経過することが多く、まれに腹痛や下痢などの消化器症状がみられます。
📚 感染症まとめ|クイズで登場した疾患を再チェック!
寄生虫とは
- 寄生虫とは、自分が生きていくために他の生物(宿主)の体内や体表に生活の場を求め、栄養や生存に必要な条件を依存する生物です。
- 寄生虫の中には、一生涯を宿主の体内で過ごすもの(例:回虫)のほか、成長過程のある段階でのみ寄生生活を送るものがあります(例:マラリア原虫など)。
- 1種類の寄生虫が、成長過程で複数の異なる宿主を利用することもあり、それらの宿主は「中間宿主」や「最終宿主」と呼ばれます。
- 寄生虫は、大きく原虫と蠕虫に分類されます。
原虫とは
- 原虫は、単細胞の真核生物で細胞壁を持ちません。
- 主な流行地は熱帯・亜熱帯ですが、日本においては輸入感染症がほとんどです。
- 代表疾患として、マラリア、赤痢アメーバ症、トキソプラズマ症、トリコモナス症などがあります。
マラリア
- マラリア原虫がハマダラ蚊の吸血時にヒトへと伝播される感染症です。
- マラリア原虫はヒトの体内に侵入すると、まず肝臓で増殖し、その後赤血球内で急速に増殖を繰り返します。
- 国内では輸入感染症としての発症がほとんどです。
- 代表的な症状として、周期的に発熱(間欠熱)を繰り返すほか、貧血や脾腫を伴うことがあります。
- マラリア原虫の種類には、三日熱マラリア、卵形マラリア、四日熱マラリア、熱帯熱マラリアの4種が主に知られています。
- 予防にはワクチンがあります。
トキソプラズマ症
- トキソプラズマ原虫の経口感染による人畜共通感染症です。
- ネコの糞便中や家畜の筋肉中に存在するため、ネコとの接触(糞便の処理など)や加熱不十分な食肉の摂取などが主な感染経路となります。
- 不顕性感染が多く、抵抗力の弱い乳幼児や免疫不全患者が発症します。
- 妊婦の感染による先天性と、日和見感染症としての後天性があります。
蠕虫とは
- 蠕虫は多細胞真核生物で、線虫類、吸虫類、条虫類に分類されます。
| 分類 | 特徴 | 代表疾患 |
| 線虫類 | 細長い円筒状の蠕虫。 経口感染するものが多い。 一部は媒介昆虫を介する(例:フィラリア症) | アニサキス症、回虫症、フィラリア症など。 |
| 吸虫類 | 主に体幹の端と腹部に2個の吸盤をもち、 扁平で左右対称な虫体。 | 日本住血吸虫症、肝吸虫症、肺吸虫症など |
| 条虫類 | 消化管を持たないため、ヒトの消化管に寄生し、体表から栄養を吸収する。 全て経口感染する。 感染源は肉や魚の生食・加熱不十分 | 日本海裂頭条虫症、無鈎条虫症、包虫症など |
回虫症
- 回虫症は、ヒト回虫(Ascaris lumbricoides)の成熟卵を口から取り込むこと(経口感染)で起こります。
- 回虫の成熟卵は主に糞便で汚染された土壌や水、野菜などに付着しており、これらを十分に洗わず、または加熱せずに摂取することで感染が成立します。
- 経口摂取により取り込まれた成熟卵が小腸で孵化し幼虫となって、血液・リンパ液にのって肝や肺を通り、小腸に戻って成熟します。
- 幼虫が肺を通過するときに好酸球が増加し、一過性の肺炎症状(レフレル症候群)を引き起こすことがあります。
レフレル症候群(Löffler症候群)
- 寄生虫の幼虫が肺に移行する際に起こる一過性の好酸球性肺疾患です。
- とくに回虫症などの腸管寄生虫で典型的に見られます。
- 主な症状は、咳嗽、喘鳴、軽度の発熱などで、胸部X線では一過性の肺浸潤影が確認されることがあります。
- 通常は、幼虫の移行が終了すると症状や陰影は自然消失します。
アニサキス症
- アニサキス属の線虫が起こす寄生虫感染症です。
- イルカやアザラシなど海洋哺乳類を最終宿主とし、サバ、アジ、イカなどの魚介類を中間宿主とします。
- ヒトは本来の宿主ではなく、魚介類を生または加熱不十分な状態で摂取した場合に偶発的に感染します。
- 主に胃壁への侵入により激しい腹痛などの急性腹症様症状を引き起こします。
- まれに蕁麻疹やアナフィラキシーなどのアレルギー症状を伴うこともあります。
フィラリア症
- 線虫の一種であるバンクロフト糸状虫やマレー糸状虫などが、蚊(アカイエカなど)に媒介され、リンパ系に寄生することで発生します。
- インド、アフリカ、中南米、東南アジアなどの熱帯地域で流行しています(日本では根絶)。
- リンパ節炎を引き起こし、乳び尿(リンパが混じった尿で、リンパ中の脂肪により白濁して見える)や陰嚢水腫がみられます。
- 慢性化により、下肢や陰部の重度のリンパ浮腫と皮膚の肥厚を伴う象皮病へと進展することがあります。
住血吸虫症(日本住血吸虫症)
- ミヤイリガイなどの淡水産の貝を中間宿主とする住血吸虫が皮膚から侵入(経皮感染)して発症する寄生虫感染症です。
- 住血吸虫が皮膚を通じて体内に侵入すると、血液の流れに乗って静脈系の血管内(門脈系など)へ移動します。
- 門脈系での産卵により血管の虫卵塞栓をきたし、大腸潰瘍や肝線維化の原因となります。
- 国内での新規感染例はなく、輸入感染が問題となります。
- 治療には、プラジカンテル(第一選択)が用いられます。
肝吸虫症(肝ジストマ症)
- 寄生虫のメタセルカリア(休眠幼虫)を含む淡水魚を生、もしくは加熱不十分な状態で食べることにより感染が成立します。
- 寄生虫が胆管や胆嚢に寄生することで、胆管炎・胆嚢炎を繰り返し、発熱や黄疸、右上腹部痛などの症状を引き起こすことがあります。
- 長期間にわたって感染が持続すると、胆管の慢性炎症・線維化が進行し、まれに胆道癌(胆管癌や胆嚢癌など)の原因となることがあります。
- 治療には、プラジカンテルが用いられます。
肺吸虫症
- 肺吸虫症は、ウェステルマン肺吸虫(Paragonimus westermani)や宮崎肺吸虫(P. miyazakii)などによる寄生虫感染症です。
- 感染源となるのは、サワガニやモクズガニ、イノシシなどの生肉・加熱不十分な肉類に含まれるメタセルカリア(休眠幼虫)で、経口摂取によりヒトの体内に侵入します。
- 虫体は腸管を通過し、腹腔・横隔膜を経て肺へ移行し、成虫として肺に寄生します。
- ウェステルマン肺吸虫症では、血痰や咳嗽などの結核様症状を呈します。
- 宮崎肺吸虫症では、胸水貯留や自然気胸などの胸膜症状が中心です。
- 治療には、プラジカンテルが有効です。
日本海裂頭条虫症
- 日本海裂頭条虫という条虫(サナダムシ)がヒトの消化管に寄生して起こる感染症です。
- ヒトが最終宿主となる際、寄生虫は主にサケやマスなどの中間宿主の生食を通して体内に入り、腸内で成虫へと成長します。
- 寄生してもほとんどの場合、無症状か軽症(腹痛、下痢、吐き気など)です。
無鈎条虫症
- 主に牛肉に寄生する無鈎条虫によって引き起こされます。
- 加熱不十分な牛肉を食べることで感染し、小腸に成虫が寄生します。
- 症状は軽度または無症状のことが多いですが、下痢や腹部の不快感などを引き起こすことがあります。
包虫症(エキノコックス症)
- キツネやイヌなどのイヌ科動物を終宿主とする寄生虫(Echinococcus multilocularis など)の虫卵を経口摂取することで感染します。
- 虫卵は小腸で孵化し、腸壁を通って血流に乗り、主に肝臓へ移行して嚢胞※状の病変(包虫嚢胞)を形成します。
※嚢胞は上皮や結合組織に囲まれた閉鎖性の袋状構造で、内部には液体・漿液・粘液・壊死組織などを含むことがあります。 - 感染後は数年〜十数年の無症状期間を経て、肝腫大・肝機能障害・閉塞性黄疸・消化管出血などを引き起こします。
- 腫瘍様に浸潤・増殖することがあり、重症例では死に至ることもあります。
- 治療には、外科的切除+抗寄生虫薬(アルベンダゾールなど)が行われます。
📄 記事の問題をPDFでダウンロードできます!
この記事の5択クイズを、印刷しやすいPDFにまとめました。
“parasite_infection_quiz” をダウンロード parasite_infection_quiz.pdf – 187 回のダウンロード – 616.97 KB✏️ クイズ形式で覚えたい人はこちら
この記事の内容をクイズ形式で確認できます。
一問一答形式で選択肢一つ一つをじっくり復習できるクイズと5択クイズでサクッと復習できるクイズの2種類を用意しています。
🔗 その他の感染症の記事はこちら
感染症に関する復習用記事を、テーマごとに分けてまとめています。
それぞれの記事では、5択クイズ+要点解説で重要ポイントをしっかり押さえられます。
苦手な分野や気になるテーマを重点的に確認したい方はこちらから👇
🔗【病原体の種類】5択クイズで理解!細菌・ウイルス・真菌・寄生虫の違いを整理しよう
🔗【感染症の基本】5択クイズで確認!日和見感染・感染経路・血液所見・ワクチンを理解しよう
🔗【感染症の分類】5択クイズで覚える!感染症法で定められた1〜5類感染症
🔗【抗酸菌】5択クイズで覚える!結核・ハンセン病・非結核性抗酸菌症
🔗【人獣共通感染症(人畜共通感染症)】5択クイズで覚える!ペスト・炭疽・ブルセラ症・野兎病・リステリア症
🔗【その他の細菌感染症①】5択クイズで理解!ジフテリア・百日咳・破傷風
🔗【その他の細菌感染症②】5択クイズで理解!猩紅熱・髄膜炎・レジオネラなど6疾患
🔗【性感染症】5択クイズで覚える|梅毒・淋病・クラミジア・トリコモナス・軟性下疳
🔗【スピロヘータ・クラミジア・リケッチア】5択クイズで覚える|重要7疾患
🔗【中枢神経系の感染症とCJD】5択クイズで総復習!ポリオ・日本脳炎など7疾患
🔗【その他のウイルス感染症①】5択クイズで覚える|デング・ラッサ熱・ヘルペス・麻疹など9疾患
🔗【その他のウイルス感染症②】5択クイズで覚える|肝炎・HIV・流行性耳下腺炎など6疾患
🔗【真菌感染症】5択クイズで覚える!白癬、カンジダなど代表的な6疾患
🖊️ 5分で復習できるクイズ記事はこちら
苦手な分野がはっきりしている方は、まずテーマごとのクイズで集中的に復習してから、総合問題に進むのがおすすめです。
以下のクイズでは、総論・細菌・ウイルス・真菌・寄生虫などの感染症を分野別にチェックできます。
1テーマあたり短時間で解けるので、空いた時間に少しずつ取り組めます。
👇 気になる分野から、ぜひチャレンジしてみてください。
🔗【5分で復習】感染症①|病原体・基本・分類をクイズでチェック!
🔗【5分で復習】感染症②|食中毒・抗酸菌感染症をクイズでチェック!
🔗【5分で復習】感染症③|人獣共通感染症・その他の細菌感染症
🔗【5分で復習】感染症④|スピロヘータ・クラミジア・リケッチア・性感染症
🔗【5分で復習】感染症⑤|ポリオ・デング熱・ヘルペスなど多彩なウイルス感染症をクイズで確認!
🔗【5分で復習】感染症⑥|ウイルス性肝炎・HIVなどのウイルス感染症と真菌感染症をクイズで確認!
👇 総合問題はこちらからチャレンジ!
🔗【感染症クイズ総まとめ】一問一答&5択で300問以上に挑戦!隙間時間で基礎力アップ!
📚 感染症全体の一覧や分類を一度に整理したい方は、こちらの記事もどうぞ
👉【保存版】感染症クイズ&解説記事一覧|覚えにくい感染症を一気に攻略!

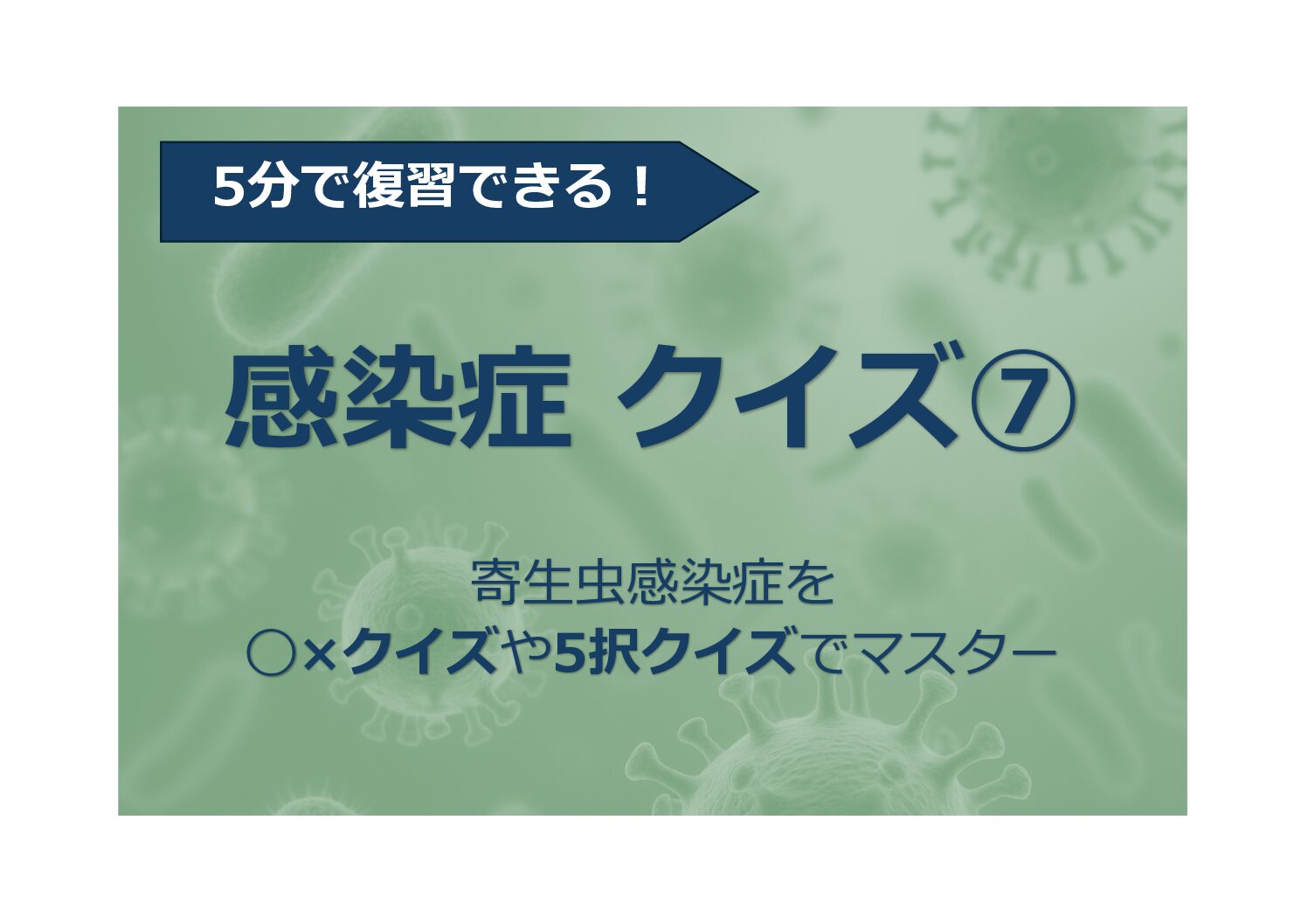

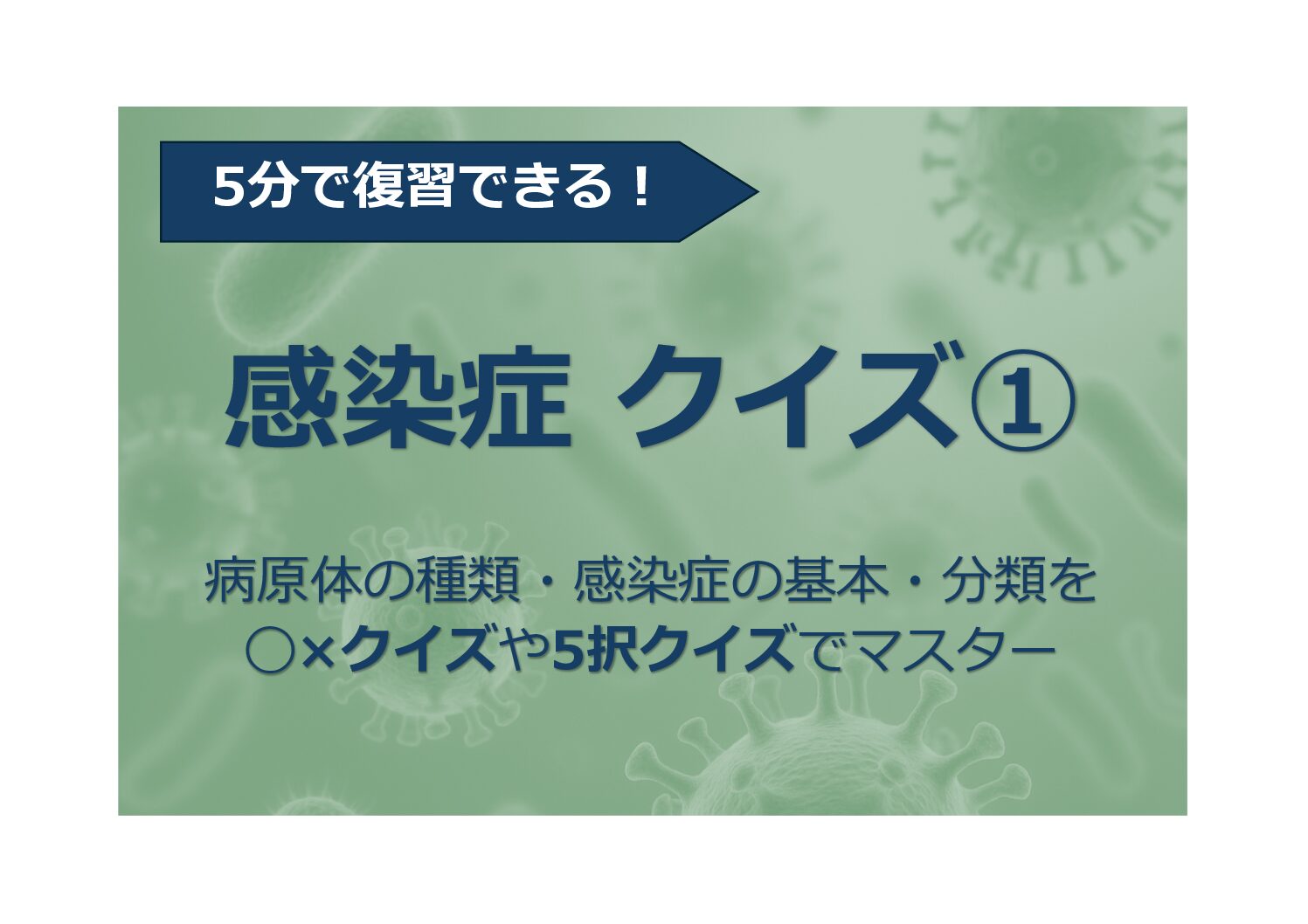
コメント